対売上高物流コスト比率(JILS 2005年度調査) 42兆円の6% 2.5兆円
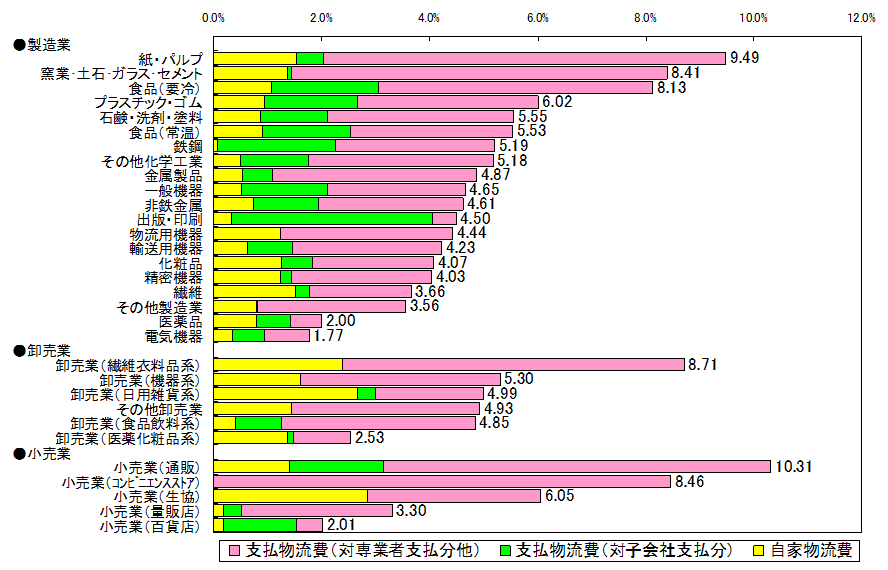
1)競争入札による単価引き下げには、自ずと限界がある。
荷主なら、単価だけでなく、輸送の仕組みを変えて総費用(単価×数量)を削減する方法を考えるべきである。
市場競争が機能しているのであれば、不況時に低下しても好況時には上昇する。
市場競争が機能しているのであれば、不採算点以下の低い単価への応札は無くなる。
輸送量減少時には、変動費だけでなく、事業存続のために間接費を含めた損益分岐点の見極めが大切である。
2)許可制時代の重量・距離帯別運賃にとらわれない視点をもつべきである。
重量・距離帯別運賃は、許可制時代の一種の便法であり、現在のビジネス環境に対応していない。
発生費用は、車種、輸送効率、積載率等、多様な条件で変化する。
物流事業者は、荷姿や輸送条件に対応した合理的な運賃体系を提案すべきである。
3)対売上高物流コスト比率はベンチマークにならない。
対売上高物流コスト比率の決定要因は、極めて複雑である。
その業種別比率を見ても、現代の企業の多くは業種横断的な多品目生産を行っているので比較にならない。
*輸送や保管は、重量や容積に左右される部分が多い。
工業統計表から、重量や容積と商品価格の関係だけをみても、その比率は多様である。
*売上高は、流通段階によっても異なる。
製造、卸、小売といった流通段階別に、流通マージンの追加に伴って売上高はアップしていく。
*物流費の負担者が、製造側か小売側かといった商慣行によっても、分子と分母は変化する。
センターフィーに代表されるように、同費用を、店舗向け仕分け・配送費として物流コストの一部と見なすか、大手小売向けの 販売促進費の一部と見なすか、あるいは製造原価と見なすかによって、商慣行の考え方次第で、対売上高物流コストの分子 と分母が変化し、同じ実態でも比率は30%以上変動する。
*企業組織を変えると物流コストが変化する。
「ロジスティクス」という包括的視点が話題になってから久しいが、多くの企業内では、工場の調達物流費と製品の販売物流 費を一括して評価している例は意外と少ない。調達費用は製造原価に含まれ、販売物流費のみが物流部の範囲となって物 流費扱いされていることも多い。
「氷山の一角説」で自家物流費や間接費を着目するべきであるとの指摘も行われたが、物流業務の多くを外部委託し本社が 管理業務のみを行うようになると、企画・管理業務の間接費は物流コストから除外される場合が多い。物流子会社が本社以 外の第三者向け業務を幅広く展開するようになると、この間接費の配分は一層わかりにくくなる。
4)価格は需給で変化する。
海運の場合には、船腹量と輸送需要の関係で需給調整が話題になるが、同じ問題は他の輸送機関にも存在する。
また、輸送量の総量だけでなく、輸送効率に影響する輸送需要の方向性も重要である。
都道府県相互間の輸送量でみても、上り下り両方向の輸送需要がある都道府県相互ペアはわずかである。
このことは、単純往復では、空車が多くなることを意味する。
空車距離の削減には、輸送需要の多い区間での復荷輸送をできるだけ長い距離で確保する仕組みが必要である。
1990年の規制緩和以降、運賃単価のマクロ数値は急速に低下し、人件費単価も同様の推移を見せている。
5)国際物流コスト
調達面でも販売面でも、輸出入依存度が高まると、物流コストもグローバルレベルで評価することが必要になる。
輸出入部分だけの輸送費であれば、国際収支統計で輸出入金額に対するサービス収支の内訳に海上・航空の貨物運賃が計上されているので、我が国の場合であれば輸出入額の約5%程度が海上・航空運賃費用比率であることが分かる。
しかし、輸出入貨物の国内輸送・保管費用は不明である。時間面でも費用面でも、ドアツードアの物流費において、国際輸送の輸出入両方の国に関わる国内物流費の割合が大きな影響を与えている。
輸送効率や輸送時間の改善を含めて、国内以上に改善の余地もあるし、多様な方法の適用も考えられるが、国内での物流改善手法の適用に比べると、ほとんど何もしていない状態に近いのが国際物流におけるコスト削減手法の適用である。
そのうえ、為替レートの変動を含め、関税や消費税等の影響があることを考慮する必要がある。