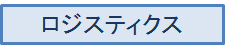
◎ロジスティクス
軍隊での兵站補給に由来するが、調達、生産、販売等に係る物流活動全般を統合管理し、その全体最適化を図ること。倉庫や物流センターにおいても、保管のみならず、荷捌き、流通加工、在庫管理等のサービスを提供し、荷主ニーズの高度化に対応すること。
◎SCM
商品供給に関するすべての企業連鎖を統合管理し、その全体最適化を図ること。原材料調達から生産、販売までを一貫したシステムとしてとらえ、消費者の購買情報を関係者が共有し、在庫の削減、リードタイムの短縮、適時・適量の商品供給等の実現を目指すこと。
◎3PL
荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の提案を行い、かつ、それを包括的に受託し、実行すること。荷主でもない、単なる運送事業者でもない、第三者として、アウトソーシング化の流れの中で物流部門を代行し、高度の物流サービスを提供すること。
◎物流改善のキーワード
・商物分離(オンラインシステム)
・情物一致(バーコード)
・大量一括輸送:物流拠点整備
・物流現場改善(トヨタ生産方式等)
◎物流部門内の改善方策
・平準化・短絡化・直送化・集約化等
・庫内動線・ロケーション管理・発生コスト分析
・入出荷・自動化・省力化
・輸配送・輸送効率・安全・環境
・人事管理(パート・アルバイト、派遣・下請)
◎コーポレートガバナンス:
会社の不正防止あるいは適正な事業活動の維持と確保
迅速な意思決定・責任の明確化・透明性の向上へ
<課題と対応>
・人数の多い役員=>役員の少数化
・形骸化した取締役会、経営会議
・取締役の経営と業務執行の兼務=>執行役員制導入
・遅い意思決定
・責任所在の不明確化
・国際競争の進展
・株主代表訴訟の頻発
<透明性向上>
・社外取締役、社外監査役の導入
◎組織再編動向
<課題と対応>
長い稟議決裁時間
係長、課長、部長、本部長、部門長、担当役員・・
=>カンパニー制による投融資・人事権の委譲
=>ビジネスユニット制によるボトムアップ型意思決定
◎業務の標準化・基幹系情報システムの活用
◎人員削減・業績評価制度の導入・早期退職制度導入
◎不良債権処理、赤字事業・低採算事業の再編・銀行の不良債権処理、株式会社格付と株価変動
株主利益重視、取引先・事業選別
◎会計システムの再編
背景:銀行の不良債権処理、株式会社格付と株価変動・株主利益重視へ
◎不良債権処理、赤字事業・低採算事業の再編へ
取引先・事業選別
有利子負債・非効率試算削減、総資産圧縮
◎国際会計基準の適用
連結会計制度の本格適用によるグループ経営見直し
部門再編、子会社事業統合・吸収合併
取得原価主義から時価会計への移行
固定資産の減損会計への移行
◎リスクマネジメント体制の強化
取引先信用力の評価
◎物流部門の位置づけ(経緯)
・営業からの分離・物流部
・物流子会社
・調達部門・生産部門
・営業組織としての物流部門:ソリューション、一括管理
◎アウトソーシング(部分業務委託から包括委託へ)傾向
・目的
企業体質のスリム化
コア業務への集中・ライバル企業との差別化
・課題
コア業務との責任分担・役割分担の明確化
委託範囲・管理範囲・業務範囲・契約関係
コスト管理・改善ノウハウの低下
品質低下・サービス低下
情報開示不十分・評価能力低下
委託料契約方式(定率等)による改善意欲の低下
◎物流部門の直面する課題
・コンプライアンス部門の独立
品質・環境・安全・情報・・
・人事問題(2007年問題→65歳定年で2012年にシフト)
・アウトソーシングと管理限界
ノウハウの喪失
現場からの遊離
・組織の水平化・分散化・権限委譲と管理限界
・「見える化」以前の「見えない問題」
・統廃合・買収・合併と一体感の再生
・グローバル展開と海外組織との連携
◎組織再編の視点
・インターネット時代における一体感の再生:目標・価値観・意欲・業務運営手法・報連相