過去の失敗に学ぶ情報化のポイントは以下のとおりです。
1)運転者に対して日常的に、安全運転やエコドライブ指導を行っていますか?
・車載機器を導入しただけでは、導入効果を発揮できません。
・車載機器は、運転指導に取って代わるものではありません。運転指導は、運行管理者が対面で行う仕事です。
・車載機器から得られたデータを活用して適正な指導を行ない、運転者が実際の運転方法を改善しなければ、事故も燃費も削減できません。
2)輸送安全規則「乗務の記録等」の情報化可能な範囲を確認していますか?
・「車載機器を導入すれば運転日報が自動的に作成される」というのは必ずしも正しくありません。
・運転日報作成に必要なデータの多くは、運転者の入力操作を含む車載機器からの取得データだけではなく、日々の運行指示内容に依存していますので、営業所の事務処理の流れをICT化と組み合わせる工夫が必要です。
・高価で多機能な車載機器を入れても、利用できなければ宝の持ち腐れになります。
自社に必要な機能を見定めて上手に活用することによって効果も発揮できます。
3)将来の経営目標に関連して情報化の範囲や担当者の位置づけが明確ですか?
・車載機器の設置だけでは、車載機器を活用できません。車載機器から入手できるデータの活用が重要です。
・データの活用には、運転者ではなく、営業所側の運行管理者や事務所ソフトの役割が極めて重要です。運行管理者のスキルアップをはじめ、営業所側の情報システムの運用体制を車載機器の導入に合わせて整えておく必要があります。
4)情報機器やソフトの更新時期を考えていますか?
・技術革新が急速に進展する昨今、情報機器やソフトの更新計画を考えておく必要があります。
急な仕様変更やシステムの拡張は、新規購入以上の費用がかかります。
・特に車載機器の取替や設置工事は手間がかかります。
機器の拡張性も考慮しつつ、最初の段階では、必要な機能に限定した車載機器の活用から始めることが必要です。
・SaaS(ASP)方式(注)のサービスの場合は、ソフトの更新が、全てセンター側で行われるので、パソコン用の事務所ソフトが不要な場合が多く、一般的には、ソフト更新の新たな投資が発生しません。
・SaaS(ASP)方式(注)のサービスの場合で、さらに車載機器との通信機能付きの場合には、車載機器のソフトがセンター側で更新されるシステムもあります。この場合は、常に最新のソフトで運用できるので、車載機器の買い換えや新たなソフトの購入・更新も不要になります。
注)SaaSはSoftware as a Service、ASPはApplication Service Providerの略
いずれもウェブ経由でのソフトウェア提供サービスのことです。
クラウドサービスも同様の機能です。
中規模事業者(車両数概ね30台以上規模の事業者)でも、IT機器を活用できる人材が少ないので、車載機器に多様な機能を求める前に、最初は、既存の運行実態に関するデータの収集分析を始めることが大切です。
特に、収集データを運行管理業務に活用して、運転日報に必要なデータの手書き作成に伴う運転者の残業代の節減等、着実な生産性向上の効果を実現することから始めることが有効です。
車載機器とIT活用のステップは、下図のように大きく四段階に分けることができます。
ICT活用のスタッフのスキルアップや会社規模の拡大、サードパーティ業務への展開などに応じて、関連機能へ拡張していくことが大切です。
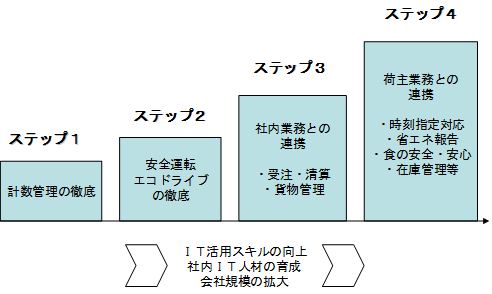
収支(コスト)管理ができていないと、何の業務が問題なのかわかりません。
コンピュータ時代以前から運行三要素(実働率・実車率・積載率)の計数管理の重要性が指摘されています。
どんぶり勘定では、問題の所在が見えませんし、効果もわかりません。
さらに台数が数十台になると、1台毎の運賃収入、走行距離や時間、運転者の健康や運転状況の管理は、社長や運行管理者の記憶だけに依存することが難しくなります。
このため、車載機器におけるデータ(計数)で各種指標やコストを「見える化」し、車両1台毎の運賃収入・燃費・走行距離をデータ(計数)として把握することが大切になります。
複雑な安全・環境・コンプライアンス対応や報告書の作成・保存を、従来どおりの事務処理の仕組みで実施していると大変な作業になります。
第一ステップとしてのIT活用や車載機器の役割は、この点にあると思われます。
運行管理業務の流れとIT活用と車載機器
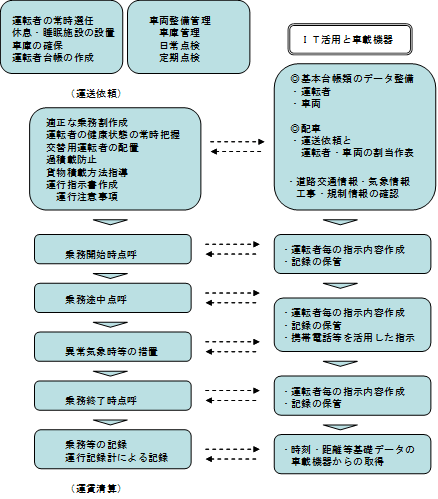
ステップ1 計数管理
計数管理は、アナログ式タコグラフの時代からトラック運送事業の経営改善に重要であると指摘されていました。
計数管理の精度向上や事務処理の迅速化・効率化が図られるチェックポイントは、以下のような項目があります。
1)帰社後・乗務後点呼のデータチェック機能
□瞬間速度超過の有無・適正速度走行のチェック
□一般道路・高速道路別にみるチェック
機器A:高速・一般の切り替えスイッチの運転者による操作
機器B:ETC車載器やカーナビとの連携による高速・一般自動切替処理
□連続走行時間のチェック
□運転者交替状況のチェック(複数カードと車両データの組合せ処理)
2)帰社後の日報作成支援機能
□速度・距離・時刻データの転送
□拘束時間・荷積降時間・待機時間・休憩食事時間等のデータ転送
□作業内容の入力データによるチェック
機器:車載機器のボタン操作やテンキー等による作業内容の運転者入力
3)経営管理用の統計データ分析機能(週次・月次・旬期等の集計)
□原価管理
□人件費の分析:給与と走行・作業内容の集計分析
□車両費の分析:走行距離・速度と車両費用の集計分析
□保険料・租税公課の分析:各種費用の距離・時間単位の集計分析
□労務管理:運転・作業時間の集計分析
□出退勤管理
機器:出退勤時刻は、車載機器ではなく、別途営業所データの利用が必要
□運転時間と作業時間の管理
機器:車載機器のボタン操作やテンキー等による作業内容の運転者入力
□営業管理:運賃収入と原価データの集計分析
□安全管理:交通事故等の発生状況と走行・作業データの集計分析
□環境管理:平均速度、最高速度、アイドリング時間の集計分析
□エンジン回転数によるギアチェンジのタイミング管理
機器:エンジン回転数データ記録機能が必要
ステップ2A 安全運転管理
安全運転管理に関連する車載機器には以下のような機能があります。
1)乗務前・乗務中点呼時の指導
□アルコールチェックをしたい:検知機器の利用
□点呼やチェック内容自体の本社での確認
□携帯電話網などを利用した通信機能とアルコール検知機器の連携
□点呼の記録:指導記録の電子ファイルによる保管と検索・分析
2)走行中の警報
□連続走行時の休憩指示(過労防止)
機器A:アラーム式
機器B:ディスプレイ表示式
(画面表示の注意に従って操作をしない場合の音声警報発生)
□休憩時の飲酒禁止の確保:
機器:飲酒時のエンジンオン不可(アルコールインターロック装置)
□走行中の危険状態に警告(速度超過、急な加減速、ふらつき走行等)
機器A:アラーム式
機器B:ディスプレイ表示式
(画面表示の注意に従って操作をしない場合の音声警報発生)
3)帰社後・乗務後点呼時の安全運転指導
□速度超過のチェック:速度記録
□過労防止:連続走行(停止)時間のチェック:速度記録
□急発進・急ブレーキ・急ハンドルのチェック
機器A:短時間の速度変化によるチェック
機器B:加速度(G)センサーデータの記録によるチェック
□車載機器の総合評価点数による指導
□映像記録型車載機器の画像にもとづく指導
□問題となる危険運転の発生場所のチェック
機器:GPS位置情報(事務所ソフトでは地図表示が必要)
ステップ2B エコドライブ管理・燃費管理
環境にやさしいエコドライブに関連する車載機器には以下のような機能があります。
1)走行中のエコドライブ指示・警報
□走行中の非エコドライブへの警告
機器A:アラーム式
機器B:ディスプレイ表示式
(画面表示の注意に従って操作をしない場合の音声警報発生)
□停止中のエコドライブ指示・警報
□アイドリングストップ
機器A:自動エンジンストップ装置
機器B:ドア開放時のエンジンストップ装置
2)帰社後のエコドライブ指導
□経済速度走行のチェック
□速度記録・平均速度のチェック
□ギヤチェンジのタイミング(エンジン回転数)のチェック
□急発進・急ブレーキのチェック
□短時間の速度変化によるチェック
□ギヤチェンジのタイミング(エンジン回転数)のチェック
□加速度(G)センサーデータの記録によるチェック
□アイドリングストップのチェック
□停止時エンジン回転有無の記録
□車載機器の総合評価点数による指導
□問題となる非エコドライブの発生場所のチェック
□GPS位置情報との併用
3)エネルギー消費量を把握したい
・帰社後のデータ取得
□走行速度データによる推計:
事務所ソフトで走行速度分布をもとに燃料消費量を推計
□燃料消費量の直接計測:
車両のエンジン制御データなどで燃料消費量を集計
ステップ3 社内業務との連携(業務効率化)
車載機器と社内業務との連携は、社内の事務処理用のデータを電子的に処理するIT活用と車載機器から得られるデータの処理を結びつけることです。
主として車載機器よりも事務所ソフトの機能に依存する部分が多い機能です。
複数のデータを組合せて分析することによって、管理精度を高め、次の改善方法を見つけることができます。
1)受注業務との連携
□受注(運送依頼)による運行指示書の作成
□配車計画システムによる運行指示書の作成
□運行計画と実績の照合による輸送効率チェック
2)清算業務との連携
□集配完了データにもとづく請求書発行
3)給与計算・労務管理との連携
□出退勤管理
機器:出退勤時刻は、車載機器ではなく、別途営業所データの利用が必要
□運転時間・作業時間等にもとづく給与計算
機器:車載機器のボタン操作やテンキー等による作業内容の運転者入力が必要
□休憩時間等の管理にもとづく過労防止
機器:車載機器のボタン操作やテンキー等による作業内容の運転者入力が必要
4)経営管理用の統計データ分析機能(週次・月次・旬期等の集計)
□原価管理
□人件費の分析:給与と走行・作業内容の集計分析
□車両費の分析:走行距離・速度と車両費用の集計分析
□保険料・租税公課の分析:各種費用の距離・時間単位の集計分析
□労務管理:運転・作業時間の集計分析
□営業管理:運賃収入と原価データの集計分析
□安全管理:交通事故等の発生状況と走行・作業データの集計分析
□環境管理:平均速度、最高速度、アイドリング時間の集計分析
5)運送状況確認との連携
□帰社時刻の確認
機器A:GPS位置情報
機器B:車載機器のボタン操作やテンキー等による運転者入力
□緊急集配依頼への最寄車両集配指示
機器A:GPS位置情報
機器B:車載機器のボタン操作やテンキー等による運転者入力
□集配先誘導
機器A:GPS位置情報による集配先への誘導口頭指示
機器B:カーナビによる誘導・さまよい輸配送回避
□道路交通状況の情報共有
機器A:道路情報(渋滞・事故情報)の入力・通信機器
機器B:カーナビによる情報閲覧
ステップ4 荷主業務との連携(新規顧客開拓)
荷主とのIT連携によるサービスの向上、輸配送ニーズの高度化への対応機能としては、以下のような車載機器の活用がみられます。
1)運送状況・入出荷状況問い合わせへの対応
□リアルタイムな車両(貨物)情報の荷主への提供
共通機器:通信機器
車両位置情報と集配状況を荷主に送信するための携帯電話等の通信機器が必要です(携帯電話の通信網を利用して自動送信する機器があります)。
顧客の貨物集配情報を直接ウェブサーバで閲覧可能にする方法と、事業者側のウェブサーバで確認して連絡する方法があります。
機器A:GPSによる車両位置情報の把握が必要です。
機器B:集配情報を配信する際はテンキーボード等の入力端末が必要です。
機器C:入出荷貨物の明細を配信するにはバーコードリーダと通信機器が必要です。
□貨物に関わる温湿度・振動等の情報の荷主への提供
機器:所要の情報に応じて、温度センサー、加速度(G)センサー等のセンサー機器によるデータの記録が可能です。
センサーの設置場所は多様です。
データの提供方法には、以下のような方法があります。
(1)ウェブサーバ経由での配信
(2)車載プリンタによる出力データの手渡し
(3)ICカードのメモリー機器経由での電子データの転送
2)緊急集配依頼への迅速な対応
□走行中の指示
機器:GPS位置情報をもとにした最寄り車両への緊急集荷指示